音楽からダイナミクスを失わせる過剰な音圧競争の行方とは?
- 音圧
- AIプラグイン, DAWソフト, RMS, ダイナミクス・レンジ, マキシマイザー(Maximizer), 音圧, 音圧競争
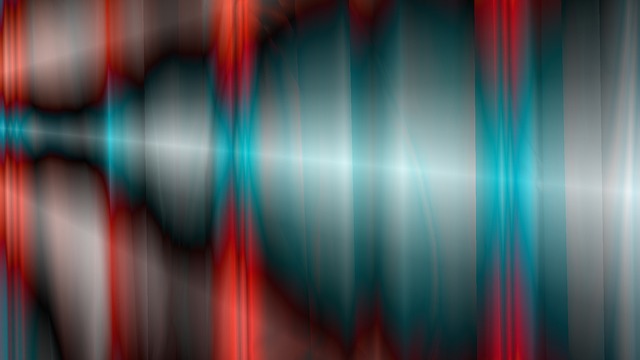
「音楽業界において音圧競争が激化している」と言う事実は、何も今に始まった事では無く、かなり前から見られた現象である。そして、DTMerはもちろん、一般リスナーでもこの事実を認識していた人も少なくないかと思う。
特に、J-POPを始め海外のEDMにおいてその傾向が強いように個人的には感じる。また、Sound Cloud等インターネット上にアップロードされる楽曲にしても、音圧が非常に高い楽曲をよく目にする。すでに何年も前からプロだけではなくアマチュアの間でも音圧競争は常態化している。
昨今の音圧競争に関して

あまりにも過剰な状態
個人的な意見を言わせてもらえば、昨今の音圧競争はあまりにも過剰な状態にあるように思える。
J-POPや海外のEDMなどプロの楽曲はもちろん、Sound Cloudなどインターネット上にアップロードされる楽曲にしても音圧が非常に高い楽曲が多くあり、「すでにプロだけではなくアマチュアの間でも音圧競争は常態化している」と言えるかと思う。個人的には、ダイナミクスの失われた音圧の高すぎる楽曲は単純に聴いていて疲れるし、画一的に感じてしまう。
市販CDのRMSは?
場合によって変わりますが、市販CDの場合はRMSで-10dB~-8dB程度の場合が多いのではないでしょうか。
(参考書籍:デジタル用語事典 ○○って何ですか? )
つまり市販CDの場合、「聴感上常に-10dB~-8dBの音量が出ている物が多い」と言う事だ。が、もちろんこれは1つの見解であり、更にこの書籍の初版発行がなされたのは2014年となっており確かな事は言えないが、この時点よりも市販CDの平均的なRMSが上がっている可能性は捨てきれない。この数値を上回る市販CDが多くあっても何ら不思議ではない。
市販CDのRMS値について興味のある人は、RMSメーター付きのアナライザー等プラグインソフトを使用し、自身のDAW環境で確認してみるのも良いかもしれない。
音圧競争激化の理由

音圧が(異常に)高い楽曲が溢れるようになった原因として、以下のようなものが考えられる。
- 競合アーティストに負けない為
- DAWソフトの登場
- プラグインエフェクトの進化により音圧アップが容易になった
競合アーティストに負けない為
そもそも楽曲の音圧を上げるのは楽曲に「迫力を出す為」、「(聴感上の)音量を大きくする為」だが、もし自身の楽曲の音圧が競合アーティストの楽曲の音圧より低ければ、2つを並べて聴かれた際に自身の楽曲の方が競合アーティストの楽曲よりも”迫力の無い小さな音”になってしまう。
それぞれが競合アーティストの楽曲に迫力で負けない為、もしくは上回る為に音圧を上げて行った結果、「”市場の音圧競争の激化”を生んでいる」と言える。
DAWソフトの登場、プラグインエフェクトの進化
DAWソフトの登場により、DAWソフト登場以前に比べ楽曲製作への参入障壁が低くなった。個人レベルでの宅録が容易になった事で新規参入者が増え、競合も多くなった。これらが、先ほど述べたような”競合に負けない為の音圧競争”をアマチュアの間にも引き起こしているように思える。
また、プラグインソフトで簡単にミックス・マスタリングを行えるようになった事やプラグインソフトの進化により個人の宅録でもある程度の作品を作れるようになった点も音圧競争に拍車をかけている一因かと個人的には感じる。
音圧競争の今後とは?

音圧の上げしろ
いくら音圧を上げ続けようにも限界はある。
以前(数十年前)のようにダイナミクスが充分にあり、音圧もそこまで過剰に上げられていないような状態の楽曲が多かった時代から音圧競争が始まる時代への移行期にあっては、音圧の上げしろもあっただろう。が、音圧競争が始まって以降、時代とともに確実に音圧の上げしろが少なくなっていくのはごく自然な流れだ。
どこまで”のり型波形”に近づくのか?
「極限まで音圧を上げた状態」とは、一体どのような状態の事を言うのだろう?
おそらく、楽曲の頭から終わりまで一瞬の音量の減衰も無く「終始音量がピーク(0dB)を指す状態」かと思う。いわゆる、完全なのり型波形(横長の長方形)である。この形に近ければ近いほど音圧は高い事になる。
たとえ今以上に音楽業界での音圧競争が悪化したとしても、さすがに”完全なのり型波形”、もしくはそれに近い楽曲ばかりが蔓延する事は考えにくいが、非ゼロの確率を割り当てることが出来るのではないだろうか。
AIプラグインと音圧
以前、「AIが描いたレンブラントの新作」が話題になっていた。AIが過去のレンブラントの作品から彼の絵の特徴を徹底的に学習し「彼が描くであろう作品」を予測、彼の手癖や特徴を再現し完成させた。
絵画の世界にAIが参入したようにDTMの世界にもAIは導入されており、最近(と、言っても何年も前だが)では”AIプラグイン”と言う物が出てきている。「AIが楽曲を分析し、適切なミックスやマスタリングのアプローチを複数パターン提示してくれる」と、言ったような物である。著者はAIプラグインを使用した事が無く詳しくないので確かな事は言えないが、今後AIプラグインが更に進化していく過程においても次のような事が考えられる*1(もしかすれば、すでにあるかもしれない。)
それはつまり、例えばディープラーニングによって”過去数十年におけるJ-POP、EDM、Hip Hop、R&B、ジャズ、演歌などあらゆるジャンルのそれぞれ毎年上位50位以内の楽曲”のミックス・マスタリングの特徴を学習したAIプラグインがあるとして、例えばそのAIプラグインに”2010年頃のJ-POP風”に楽曲をミックス・マスタリングするよう指示を与えれば、音圧の(非常に)高い楽曲に仕上がる、もしくはそう言った方向のミックス・マスタリングにする為に適した数種類のアプローチを提案してくる可能性が高くなる、と言う事だ。

